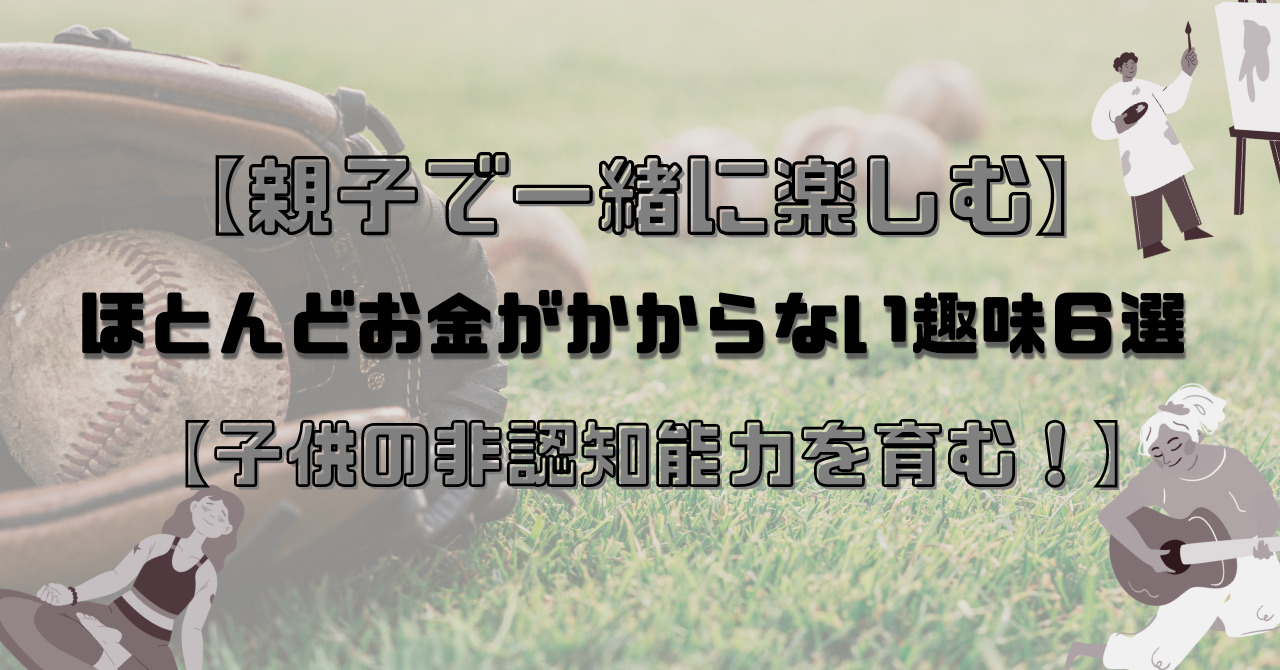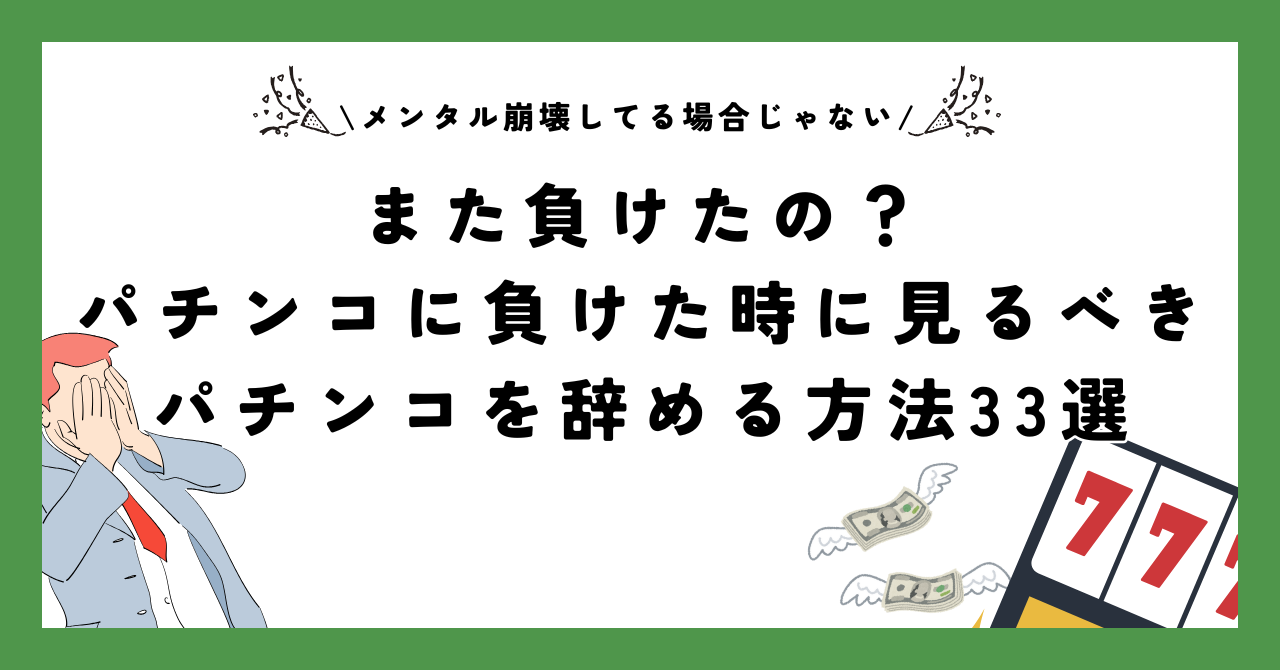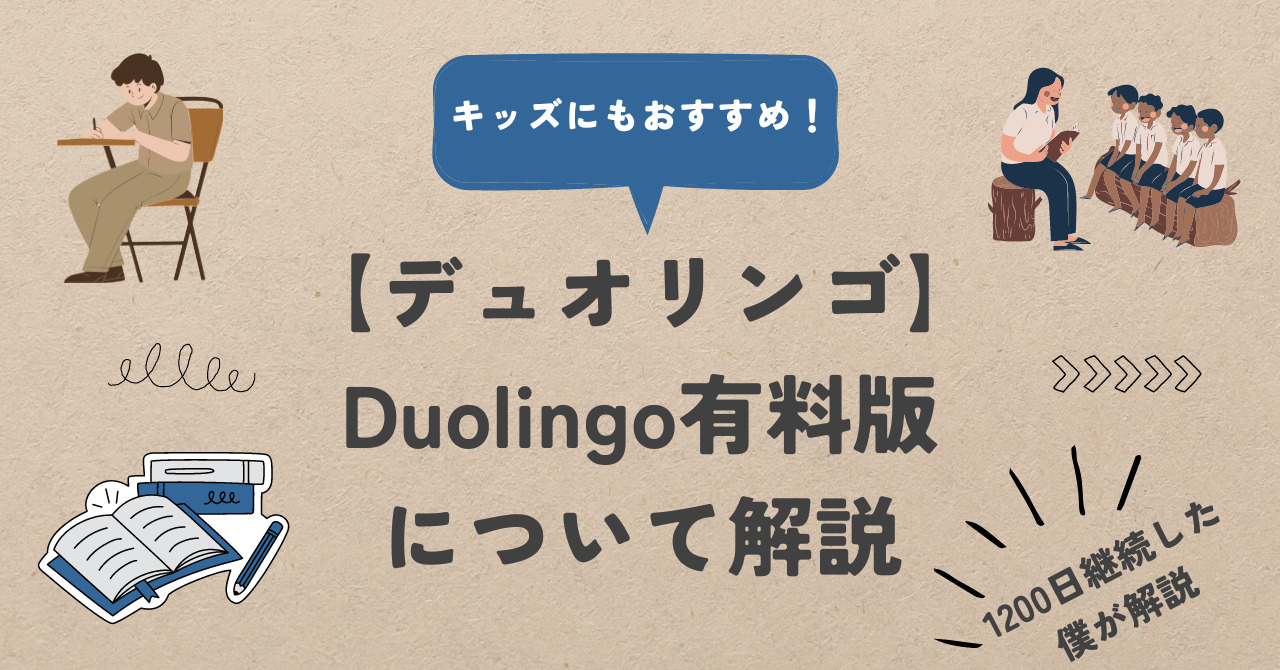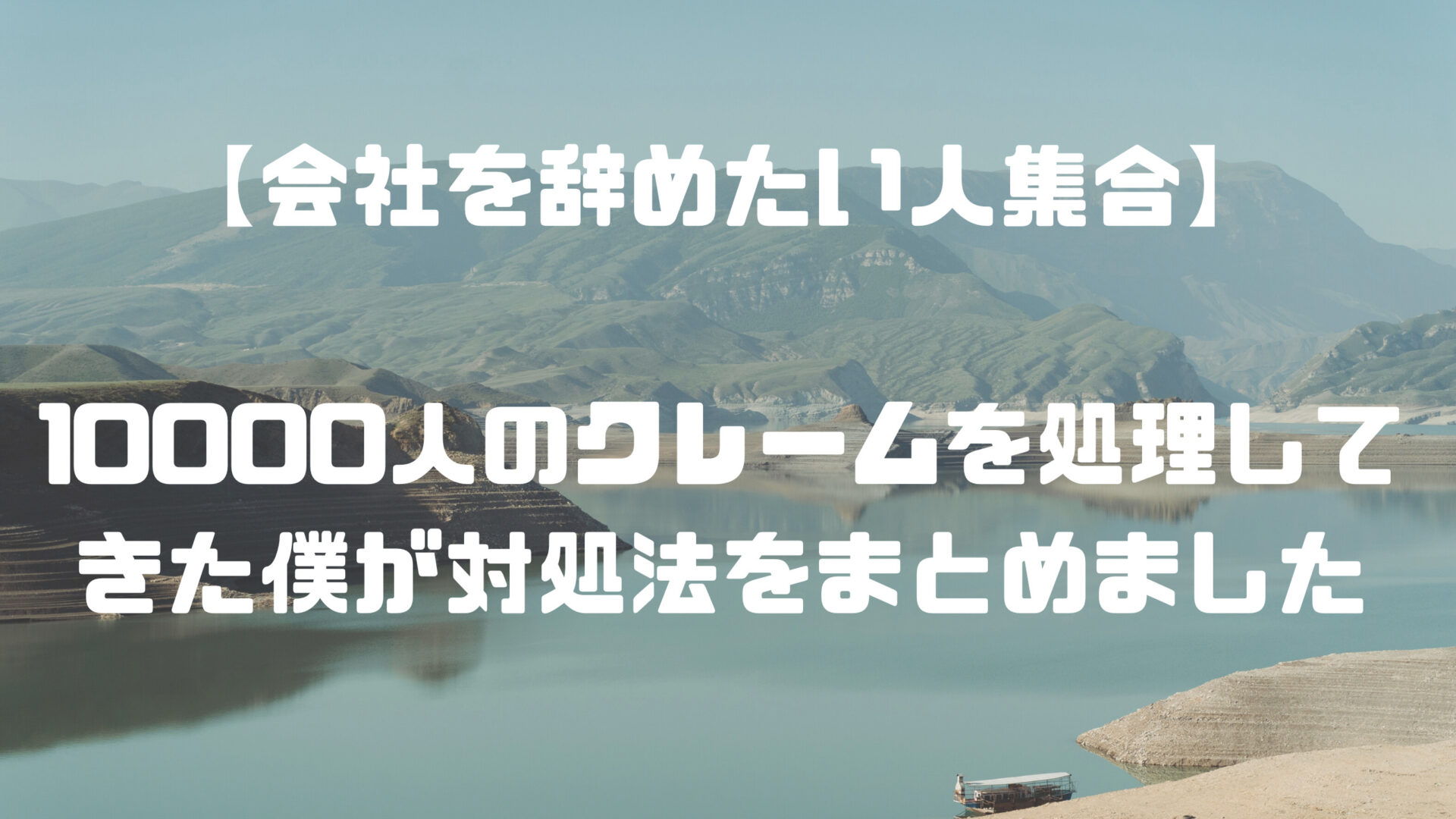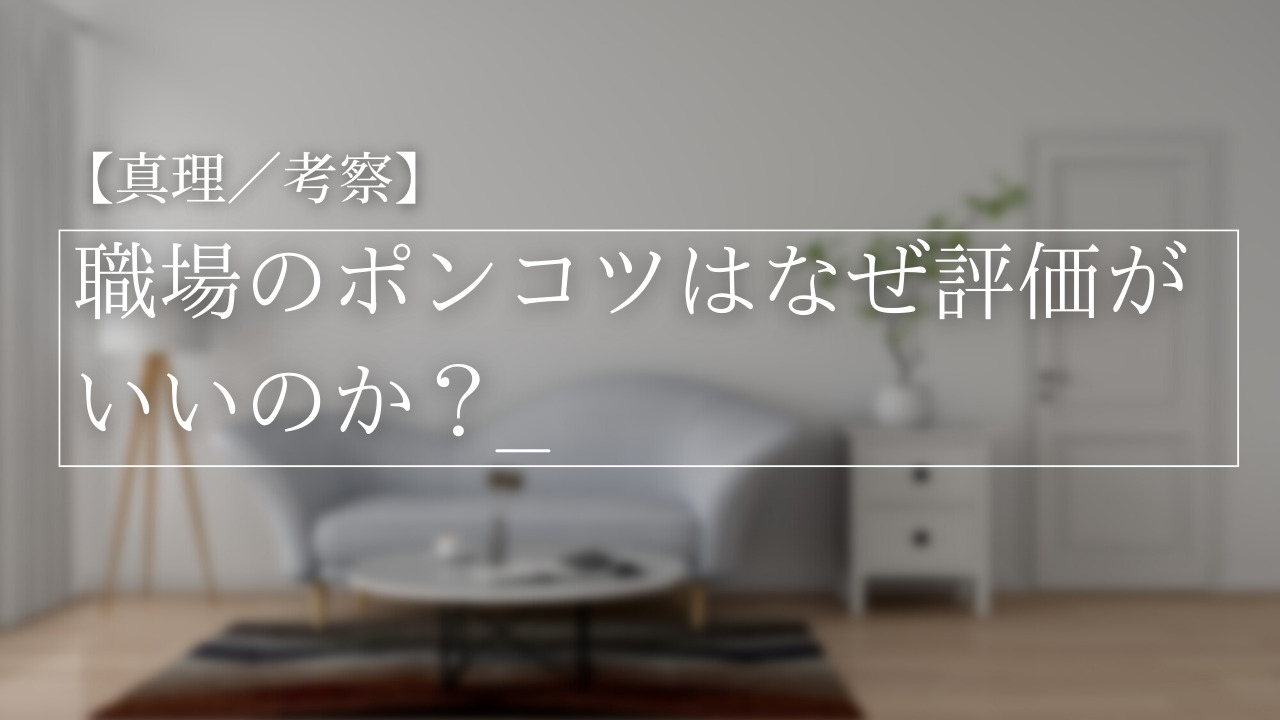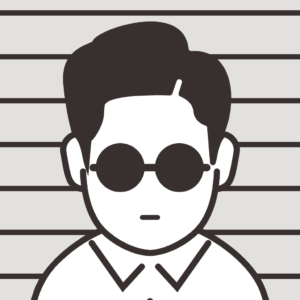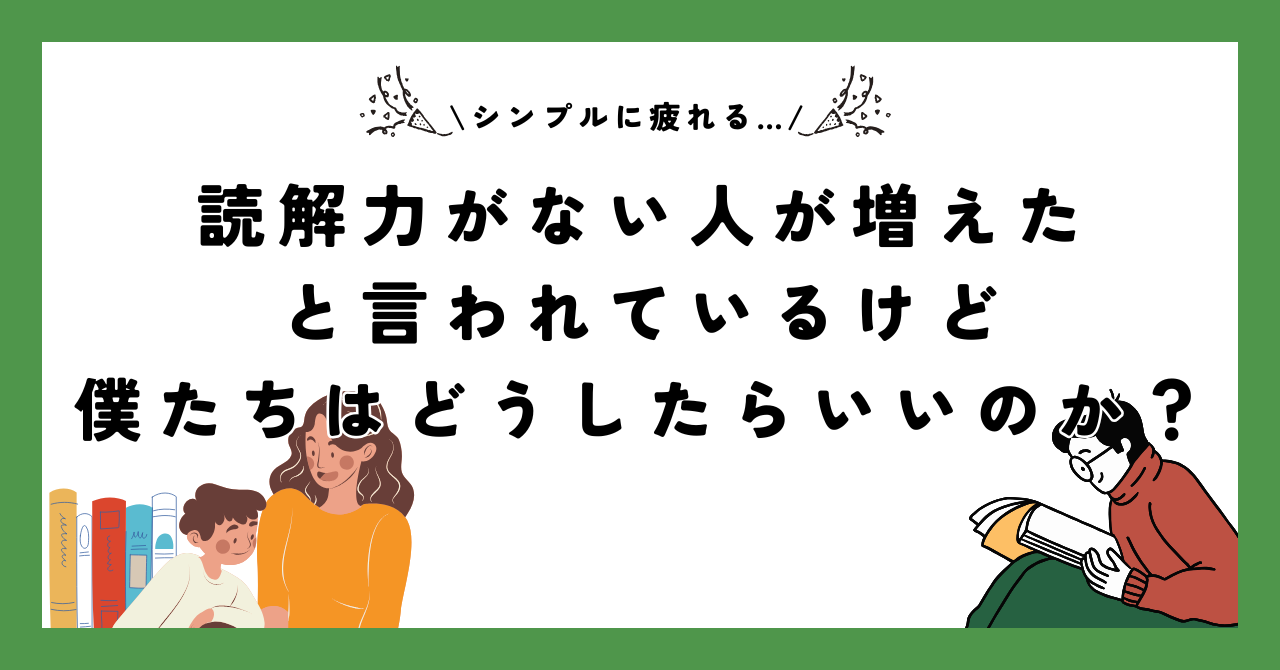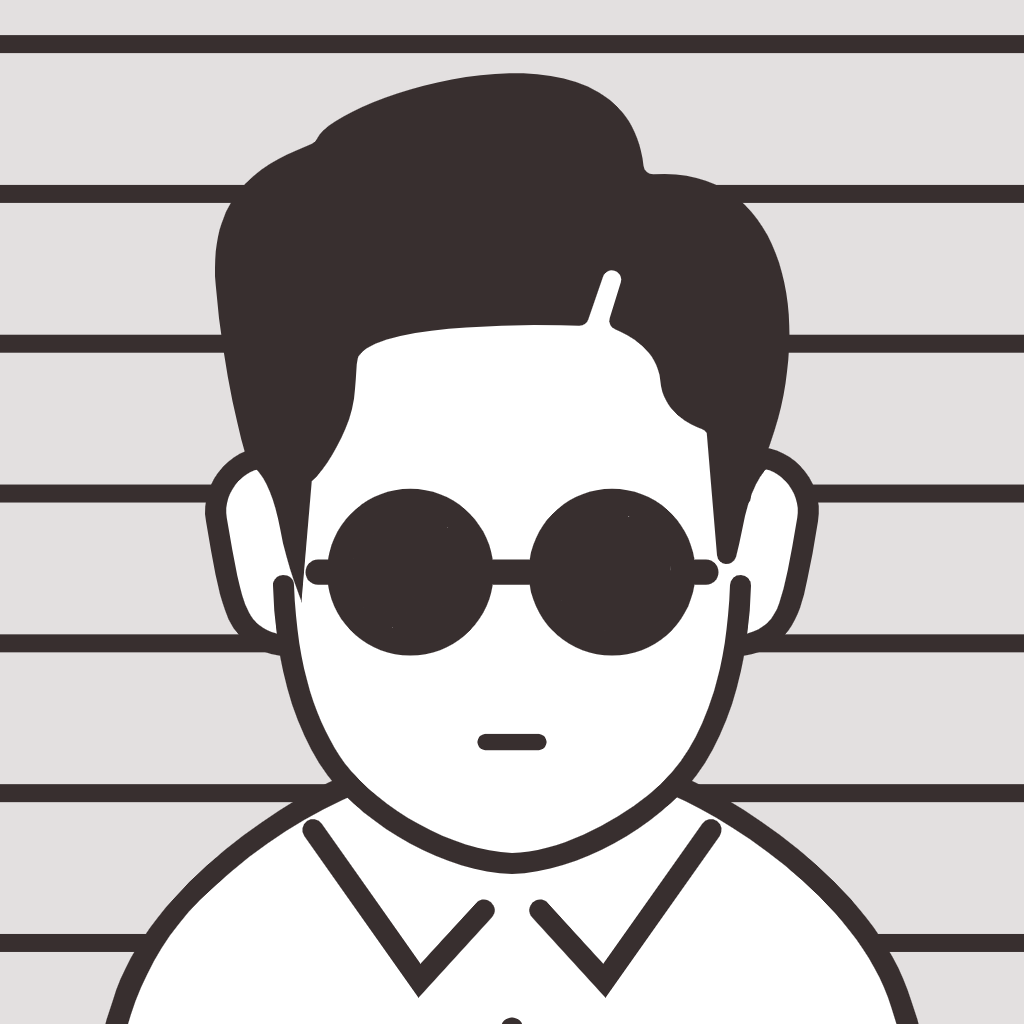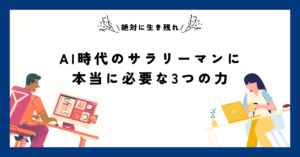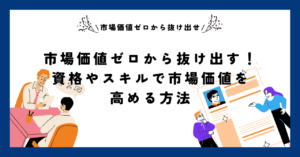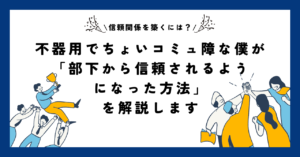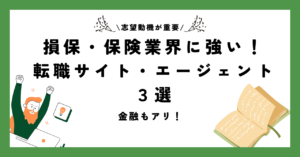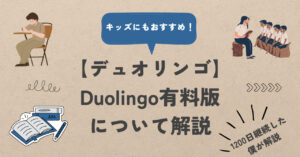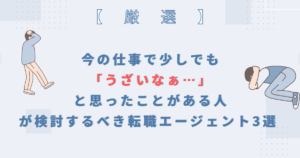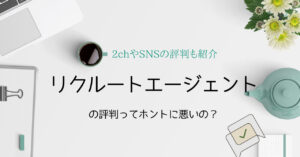「え、そこまで説明しなきゃダメなの?」
最近こんな場面が増えてきた気がします。
こんなとき、思わずこう感じたことはありませんか?
- 職場や家庭で、ちょっとした指示や連絡がうまく伝わらず、なんだか嫌な気持ちになる。
- 何度も同じことを説明させられて疲れる。
- 会話の意図が通じず、トンチンカンな返答が返ってくる。
これってもしかすると「読解力がない人、増えてない?」ってことかもしれません。
実際、文化庁が発表した「令和5年度 国語に関する世論調査」でも、約6割の人が「1冊も本を読まない」と答えており、読解力の低下が社会的に問題視されつつあります。
本日の記事でわかること
今回の記事では、この現象に対して以下のような内容を解説していきます:
- 読解力がない人って本当に増えたのか?
- 読解力がない人が増えると、私たちの生活にどんな影響があるのか?
- 読解力がない人とどう付き合えばいいのか?
- 自分自身が「読解力を落とさないため」にできることとは?
読解力がない人が増えた今、僕たちにできる簡単な対策【誰でも簡単にできる】
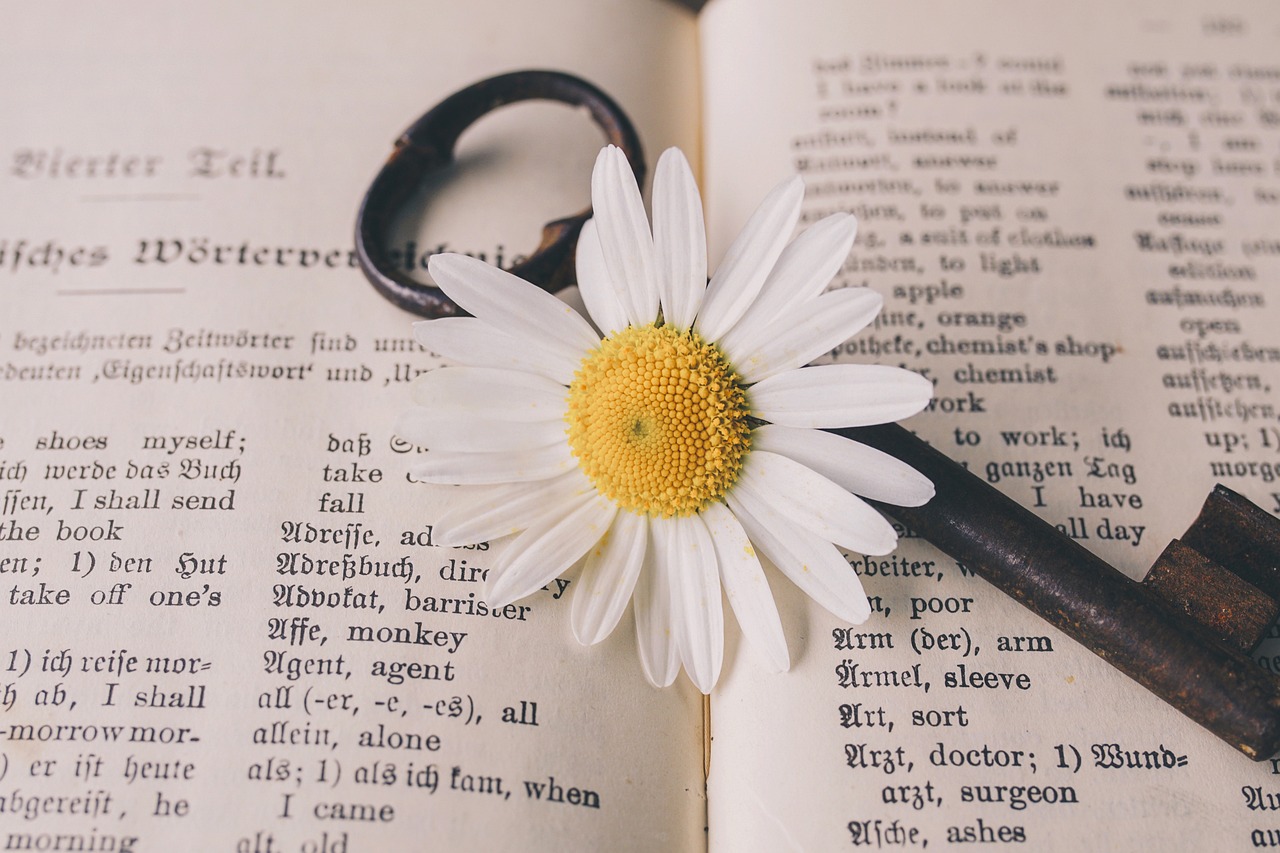
まず結論から言います。
読解力がない人が増えている今、僕たちがすべきことはたった一つ。
「読んで、意味を正しく理解できる人を少しでも増やすこと」です。
自分自身はもちろん、家族や職場の同僚、部下など身近な人たちが、文章をきちんと読めるようになるだけで、日々のコミュニケーションは驚くほどスムーズになります。これは今のような「情報過多の時代」だからこそ、ますます重要になってきています。
じゃあ、どうやったら「文章を読んで意味を正しく理解する力=読解力」を上げられるのか?
結論はシンプルで以下の3つを意識すること。
読解力を高める3つのコツ
- 読書習慣を持とう
- ネットやSNSとの付き合い方を見直そう
- 集中できる環境をつくろう
どれも基本的なことですが、ちゃんとやれば効果は絶大です。
難しいテクニックは必要ありません。
誰でも再現できることばかりです。
ここからは、それぞれについて順番に解説していきます。
読解力を上げるコツその1:読書習慣を持とう
1つ目のコツは、やっぱり読書習慣かなと。
日常的に本を読んでいる人って、やっぱり文章の理解力が高い傾向があります。
これは僕自身の経験からもそうだし、きっとあなたの周りでも思い当たる人がいるんじゃないでしょうか。
ところが最近では、そもそも本をまったく読まない人が増えています。
例えば、文化庁が発表した調査では「1カ月に1冊も本を読まない人」がなんと62.6%にものぼっているそうです。
9月中旬、文化庁が発表した「令和5年度 国語に関する世論調査」の結果が大きな話題を呼びました。1カ月間の読書量について、62.6%の回答者が「1冊も本(電子書籍含む)を読まない」と回答していたからです。
読書量が減った3つの理由とは?6割の男女が「読解力不足」を実感
https://kufura.jp/work/work-technique/562699
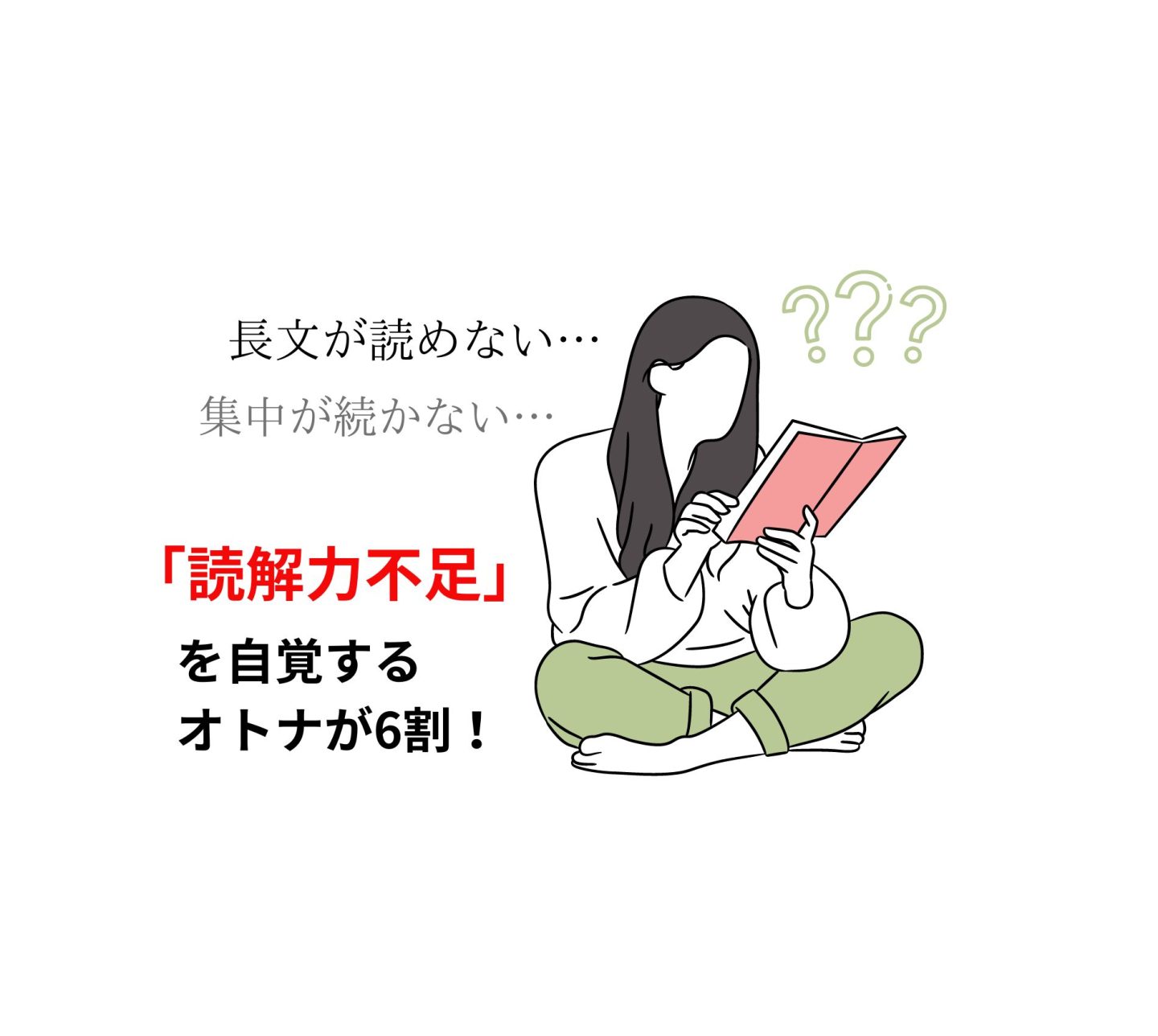
読書をすれば自然と読解力は高まるのか?
では、読書をすれば自然と読解力は高まるのでしょうか?
実はそうとも限りません。
読書=読解力アップと思われがちですが、読解力の定義を知らないと、いくら本を読んでも意味が薄くなってしまいます。
そもそも「読解力」って何?
そもそも「読解力」とは文部科学省では、読解力を次の3つの力に分けて定義しています。
PISA調査における読解力の定義,特徴等
- 情報の取り出し:書かれている内容を正確に読み取る力
- 解釈:意味や意図を理解・推論する力
- 熟考・評価:読んだ内容を自分の知識や経験と結びつけて考える力
このように、読解力は「ただ読む」だけでは不十分で、自分なりに考えて理解する力もセットで必要なんですね。
「読む」だけでは足りない理由
読書は確かに有効な手段ですが、「とにかくたくさん読めばいい」というわけではありません。
例えば、今かなり話題になっている「国語読解力「奇跡のドリル」小学校1・2年」の著者・伊藤氏貴さんも、こんなことを語っています。
多読、乱読は無駄ではありませんが、それでは真の読解力はつかないのです。
国語読解力「奇跡のドリル」小学校1・2年より引用
「読む」ことと「読める」こととは違うということを目の当たりにしました。
国語読解力「奇跡のドリル」小学校1・2年より引用
つまり、「読んで終わり」ではなく、「読んで、自分なりの意見や考えを持つこと」が大切なんです。
なので読解力を本気で上げたいなら、本を読んだあとはぜひアウトプットを意識してみてください。
そのためにも例えば、小学生向けの国語ドリルを使ってみるのもアリ。
こういった小学生向けのドリルって大人がやっても割と頭を使うので、いいトレーニングになります。
まずは“好きなこと”から始めればいい
前述の通り、読解力を上げるには小学生向けの国語ドリルがおすすめ、とお伝えしてきました。
とはいえ——
- 「ドリルとか面倒くさい…」
- 「アウトプットって言われても、何を言えばいいのかわからない…」
- 「そもそも、本読むの苦手なんだよ…」
という声が聞こえてきそうです。
僕自身、ネット社会に毒された人間なので、その気持ちは痛いほどわかります。
だからこそ、最初の一歩は「好きなことから始めてみる」のがいいんじゃないかなと。
興味のあるジャンルの本を1冊手に取ってみる。
まずは興味があることで「読む」ことに慣れるところから始めていきましょう。
いきなりアウトプットなんて意識しなくてもOKなので気軽にやっていきましょう。
何より大事なのは、行動すること。
この状況をなんとかしたいと感じたその思いこそが、読解力を伸ばす一番の原動力になるはずです。
読解力を上げるコツその2:ネットやSNSとの付き合い方を考える
読解力を上げるコツの2つ目は「ネットやSNSとの付き合い方を考える」ですね。
そもそも、読解力がない人が増えた背景には何があるか、考えたことはありますか?
実はこれ、僕たちが日常的に使っているネットやSNSが原因のひとつだと言われています。
長い文章を深く考える習慣がなくなった
どういうことかというと、僕たち現代人が情報収集の手段として使っているのは、ほぼネットやSNSですよね。
ただ、これらのツールってどうしても短い文章・表層的な内容のやり取りが中心になります。
これはこれで忙しい僕たちにとっては便利な面もあるのですが、問題なのは「それだけ」になってしまっている人が多い、ということ。
「マジヤバい」
「エグい」
「それな」
今のネットのやり取りって、こんな感じの言葉ばかりじゃないですか?
これじゃ、文章の構造を読み解いたり、文脈から真意を読み取ったりする訓練にならないっていうのは容易に想像できますよね。
こういうのが結果として、「長文に触れない → 考えない → 読解力が落ちる」という流れになってしまっているということです。
つまり、読解力の低下は、短文情報に頼りすぎた生活の積み重ねの結果ってわけですね。
ネットやSNSとの付き合い方を考える
とはいえ、「じゃあネットやSNSをやめよう!」というのは現実的じゃないですよね。
今の時代、それを完全に断つのはほぼ無理です。
だからこそ大事なのが、「付き合い方を見直すこと」なんじゃないかなと。
例えばこんな感じ👇
- スマホの通知をオフにしておく
- 時間制限系のアプリを使って利用をコントロール
- ネットを使わない趣味を持つ
- オフラインの人間関係に積極的になる
僕自身、地元の少年サッカークラブでボランティアをしていたりしますが、リアルなコミュニティに入ると、自然とネット依存から自然と距離を置けるようになります。
仕事以外の人との繋がりもできるので、かなりおすすめですよ。
もちろんネットやSNSも、使い方次第では読解力を鍛えるツールにもなり得ます。
だからこそ、この時代に求められているのは「使い方を考える力」なのかもしれませんね。
読解力を上げるコツその3:集中できる環境を作り出そう
読解力を上げるための最後のコツは、「集中できる環境を作り出すこと」です。
どんなに優れた教材を使っても、集中できなければ効果は出ません。
実際、文章を読んでいても途中で気が散ってスマホ見ちゃう人、多いと思います。
僕もそういう時期、めちゃくちゃありました。
だからまずは、「集中できる環境づくり」が大事になってきます。
集中できる環境を作るには?
「そもそも集中力がないんだけど…」という人もいるかもしれません。
でも、集中力ってある程度は環境次第で引き出せるんですよ。
例えば:
- 作業効率が上がる
- 深い思考ができて学習効率も上がる
- 集中状態に入りやすくなる(いわゆるフロー状態)
こんな感じで、環境を整えればかなり変わってきます。
僕はこうした
ちなみに僕も集中できる環境を作るためにこんな工夫をしました。
独身時代は完全な夜型人間で次の日に仕事があっても2時とかに寝るような感じでした。
しかし、結婚して子供ができると「一人の時間」というのが本当になくなります。
そうなると集中して作業する時間を確保するのが物理的に無理になってしまう。
それに社会人として仕事をしていると夜は疲れてしまっているので、集中どころの話ではなくなってくる。
だから今は朝4時に起きて、集中できる環境づくりに徹するようにしています。
結局これが一番効率よくて、ずっと継続してやってますね。
この習慣は「朝活」とも言われていて、効果や続け方については、こちらの「毎日を有意義にしたいって人がやるべきことを解説します【朝活の効果や失敗しないためのコツを実体験から解説】」で解説しています。

もちろん、人によって集中できる時間帯は違うので、「自分は朝じゃなくて夜型かも」という人はそっちを試してみるのも全然アリです。
大事なのは、自分にとって最適な環境や時間帯を見つけることですね。
この機会に問題集に挑戦するのもイイ!
集中環境の整備と並行して、「読解力用の問題集に取り組む」というのも非常に有効です。
目標があれば、集中もしやすいですし、何より結果が出やすい。
「大人が小学生用の国語ドリルやってるなんて恥ずかしい…」
なんてことは一切ありません。
実際に読解力がない大人が小学生向けの国語のドリルをやって大きな結果を出していたりします。
参考になる動画はこちらからどうぞ!
おすすめの問題集はこちら
最後におすすめの問題集をご紹介しておきます。
特に初心者向けで効果が期待できるのでこの機会に是非試してみてください。
Gakken|2分で読解力ドリル
国語読解力「奇跡のドリル」小学校1・2年向け
ちなみに我が家では、僕・妻・息子の3人で一緒にチャレンジしています。
家族みんなでやると習慣化しやすいのでおすすめですよ。
読解力がない人が増えたと言われているけど、僕たちはどうしたらいいのか?【シンプルに疲れる】のまとめ
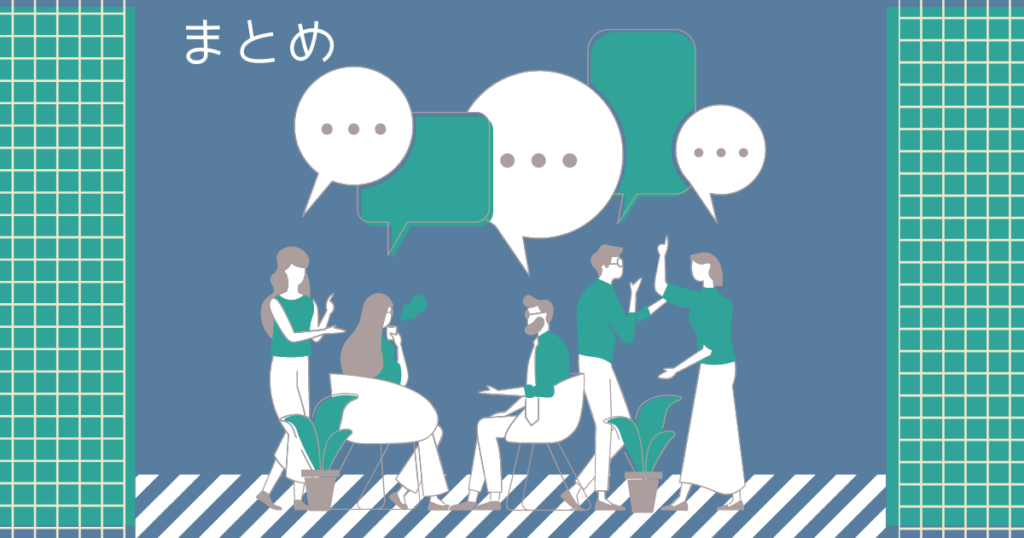
それでは最後に本日の記事のおさらいをしておきましょう。
本日の記事のおさらい
- 読解力がない人は増えている。
- 読解力がな人はこの3つで向上させられる
- 読書習慣を持つ
- ネットやSNSを制限する
- 集中できる環境を作る
でしたね。
読解力がない人が増えた今、僕たちにできることはやはり「文章を読み、内容を理解できる人を増やす」ってところです。
読解力がない人と一緒にいると、正直シンプルに疲れるんですよね(笑)
だからこそ、自分の周りだけでも少しずつ変えていければ、心地いい空間が広がっていくはず。
僕も引き続き、自分自身のアップデートを続けていきます。
この機会に、ぜひ皆さんもチャレンジしてみてくださいね!